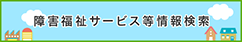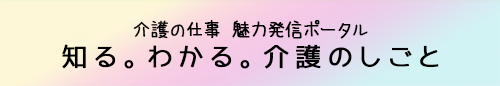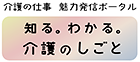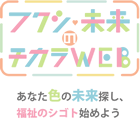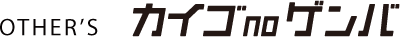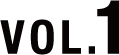
デジタルとアナログを融合したクリエイティブな発想力で、利用者様と職員の笑顔が溢れる施設に。
垂水区 特別養護老人ホーム塩屋さくら苑
業界全体でICT機器の導入が進む昨今。しかし大切なのは機器の導入ではなく、そこからいかに価値ある変化を生み出すか。法人の「セーフティケアプロジェクト」を牽引し、その可能性を真摯に追求する道村悌紀さんに詳しく話を伺った。
取材に伺ったゲンバ

- 特別養護老人ホーム塩屋さくら苑<垂水区>
- 2021年より法人全体で「セーフティケアプロジェクト」を開始。移乗用リフトや見守りセンサー、インカム、介護支援ソフトなどを導入し、利用者様・職員の両者にとって安心・安全なケアを推し進める。
身体的負担の軽減を追求する。
移乗用リフトを使うだけでは職員の腰痛は軽減しないと確信し、どうすれば身体的負担の少ないケアを実現できるかを徹底的に分析することにしたんです。作業内容を詳細に測定し、1日に何回、何時間、どのような動作をどれくらいの回数をしているかを数値化。さらに全職員へのアンケート調査で、腰痛リスクの高い作業を洗い出しました。

とにかく日常業務の全てにおいて、不良姿勢をなくしていこう、と。その試みの結果、先行して取り組んでいるメンバーから『腰痛が軽減された』『かなり楽になった』という意見が多数上がっています。
腰痛予防の取り組みがさらに浸透していけば、介護職そのものが安心して長く続けられる仕事になると思っています。

お話いただいた道村悌紀さん
「セーフティケアプロジェクト」
いわば、『利用者様と介護者の双方を守るセーフティケア』という考え方です。たとえば従来の抱える移乗方法だと、接触による感染症のリスクや怪我が発生していたのですが、移乗用リフトを導入することで利用者様の皮膚の損傷や褥瘡を減らし、職員の腰痛リスクも軽減することができました。このように、ひとつの施策で双方の安全性が高められる取り組みを推進しています。
見守りセンサーも導入して、利用者様の夜間の睡眠データを記録しています。これによって、利用者様が目を覚ます時間がわかり、睡眠を妨げずに介助を行うことが可能になります。

また、集めたデータから個々の利用者様の生活リズムが可視化されることで、「利用者様に合わせた、よりタイムリーなケア」を展開し、職員が忙しい時間帯を明確化することができ、適切な時間・場所に職員を配置できるようになりました。その結果、ケアの品質だけではなく業務の効率も向上しています。
いかに価値ある変化を生み出すか。
機器を導入するのは簡単です。重要なのは、その機器から得られたデータを活用して、介護サービスの質や職員の業務をどう改善するかなんです。
たとえば掲示物ひとつを取ってもそうなんですが、利用者様向けのものは利用者様の目線の高さに掲示して、職員が目にするものは職員の高さに配置する。これだけで、利用者様は快適に読むことができるし、職員は腰をかがめる必要がなくなります。

クリエイティブな思考の源泉とは。
新しいものを取り入れる際には、必ず今あるものを減らすようにしています。1つ増やすなら2つ減らす。新しい業務が増えるばかりだと、職員の負担も大きくなる一方ですから。
80年、90年と長い人生を歩んでこられた方々には、やはりそれだけの歴史があります。この利用者様はなぜこの動作を嫌がるのか、その原因が育ってきた家庭環境に起因しているケースもあります。その方の人生を知ることで、一歩踏み込んだケアができる。それがすごくうれしいんです。

施設は、利用者様にとって自宅に近い場所。私たちはその環境をつくっているという意識を持つべきです。職員が慌ただしく走り回ってると利用者様も不安になるし、大きい声を出していると緊張させてしまう。利用者のQOL向上のために、機器や設備を活用していきたいですね。